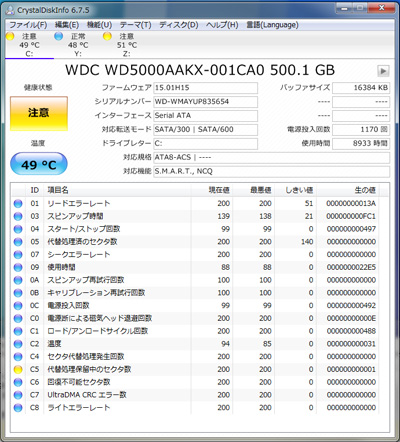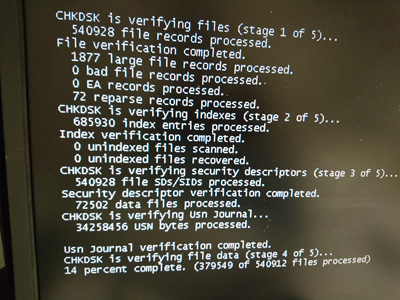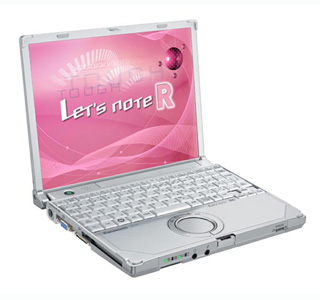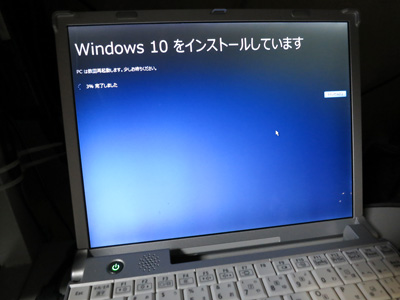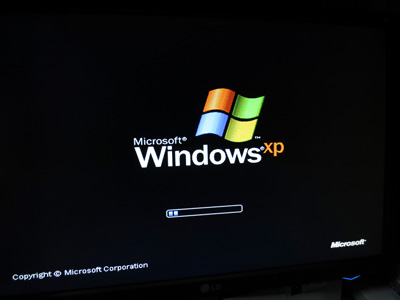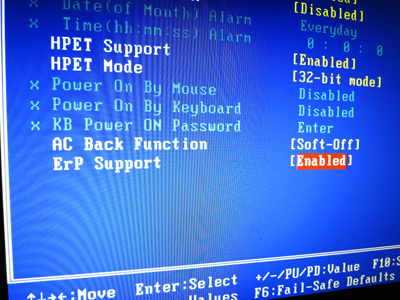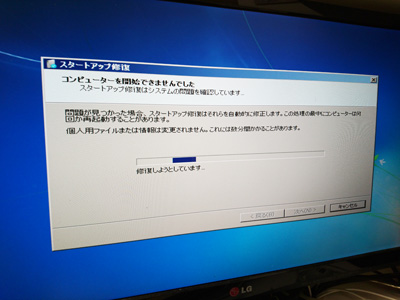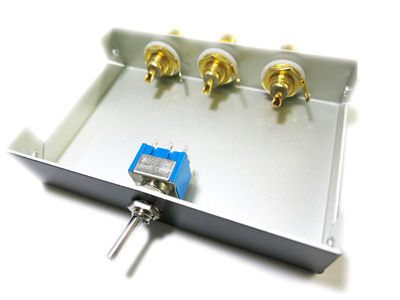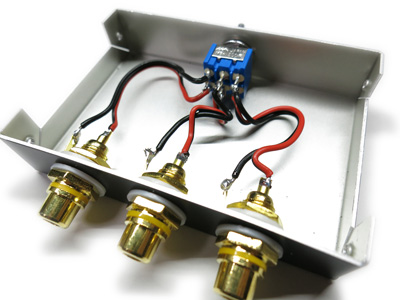廃棄するHDDをひたすら解体しました。
トルクスねじを外していく作業。
外側はT8だけど、中はT5~7くらいのが使われてて、結構面倒。
最初安い工具のを使ってたら、すぐにナメちゃったから、もうちょっと良いレンチにしたら効率も上がりました。

なんだかんだで20台くらい解体したかも。
そこから抜き出したプラッタ(の一部)。
これを読めないようにすればOKかな?
久々に静音PCの側を開けてHDDの入れ換えしました。

320GBのから余ってた500GBのにしただけなんですけどね^^;
空きが数GBになっちゃってたから。
主にmp3からm4aに音楽データを変えたから容量増えちゃったせいですね。
思ったよりホコリは溜まってなくって一安心。
CPUクーラーについたホコリはエアダスターでキレイにしました。
載せ変えて組み立てなおしてからケーブル接続、電源いれたら・・・あれ?
システム無いって怒られちゃった。
最後中をチェックしたら、SATAケーブル抜けてました^^;
刺し直してOKでした(´▽`) ホッ